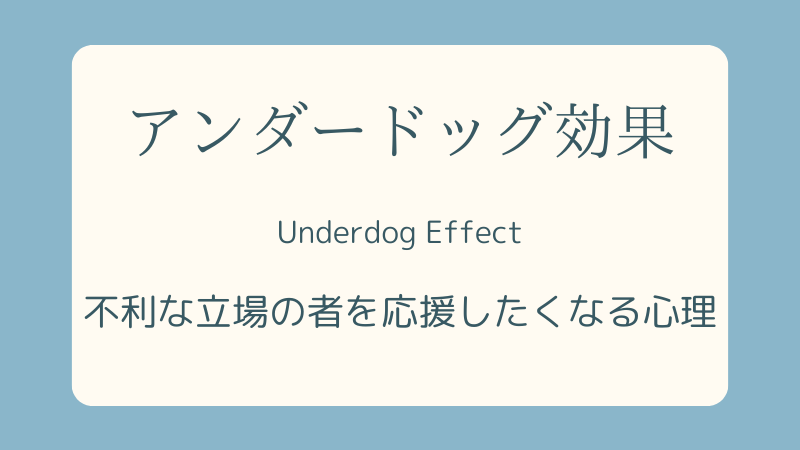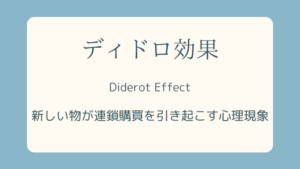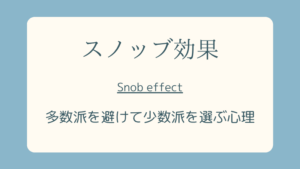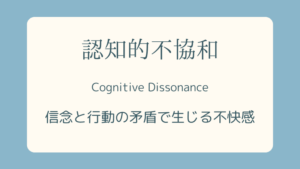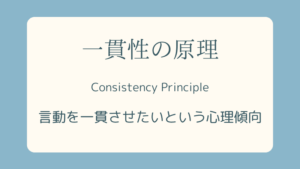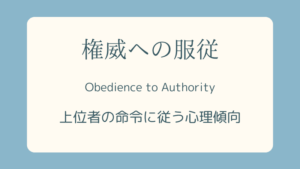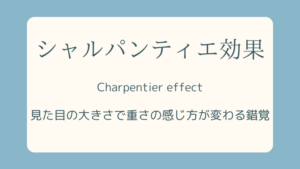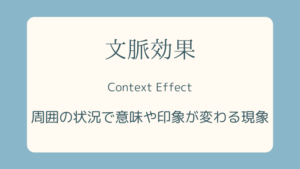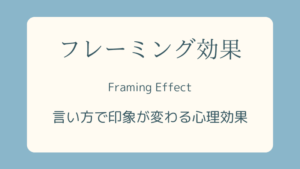この記事では、アンダードッグ効果の意味や定義をはじめ、判官びいきやバンドワゴン効果との違い、恋愛や選挙、マーケティングでの活用事例まで、幅広く丁寧に解説します。
SNSでの応援行動やビジネスでのストーリーテリングに関心がある方も、「アンダードッグ効果とは何か?」を知ることで、行動の背景がより深く見えてくるはずです。
身近な実例とともに、やさしく読み進められる内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
アンダードッグ効果とは?意味・定義を解説
「アンダードッグ効果」という言葉、聞いたことはありますか?
スポーツの試合や選挙のニュースなどで、明らかに不利な立場の人やチームを思わず応援したくなったことがある方も多いと思います。
実は、こうした気持ちの背景には、ある心理現象が関係しています。
ここでは、その「アンダードッグ効果」について、やさしく解説していきます。
「アンダードッグ」の語源と日本語訳
アンダードッグ効果とは、勝ち目が薄そうな人や立場の弱い側に対して、「頑張ってほしい」と応援したくなる気持ちが行動にまでつながる心理のことです。
たとえば、選挙で劣勢とされる候補者に投票したくなったり、下位のチームを応援したくなったりする場面です。
この現象は、行動経済学や心理学でも研究が進んでいるテーマの一つです。
もともと「アンダードッグ(underdog)」という言葉は、英語圏の闘犬競技が由来です。
19世紀のアメリカでは、戦う犬のうち、下に押さえ込まれていた側の犬を「アンダードッグ」と呼んでいました。
つまり、力のない側、劣勢な側を意味しています。
この言葉が、だんだんと比喩的に使われるようになり、「不利な立場の人」や「苦戦している側」を指すようになりました。
日本語では「判官びいき効果」と訳されることが多いです。
「判官びいき」というのは、歴史上の人物である源義経のように、不運な最期を迎えた人に同情して応援したくなるような心情を指しています。
「負け犬効果」と直訳されることもありますが、この表現だと「すでに負けが決まっている」という印象を与えるため、現在ではあまり使われていません。
アンダードッグ効果は、あくまでも「まだ結果が決まっていないけれど、今は不利な立場にいる人」への応援が広がる現象です。
劣勢な状況に心を動かされ、行動に移す人の心理には、意外と深い背景があるのです。
心理学的メカニズムを3ステップで解説
アンダードッグ効果は、ただの「同情」ではありません。
実は、心の中でいくつかの段階を経て、行動にまでつながっていく現象なんです。
ここでは、その流れを3つのステップに分けて、わかりやすく説明していきます。
まず最初のステップは、「同情」です。
たとえば、スポーツの試合で劣勢なチームが頑張っている姿を見ると、自然と「なんとか勝ってほしい」と感じることがあります。
これは、劣った立場にある人を見たときに湧き上がる感情で、人間にとってとても自然な反応です。
この点については、チャールズ・ロバート・ダーウィンさんも『人間の由来』(1871年)の中で触れています。
ダーウィンさんは、人間が進化するうえで「仲間への思いやり」や「助け合いの本能」が大きな役割を果たしたと述べました。
次のステップは、「共感」です。
もし、劣勢な立場にいる人があきらめずに努力している姿を見たら、「自分も何かしたい」と思うようになります。
このとき、応援の気持ちは一段と強くなります。
実際の実験でも、劣勢にあるブランドが「今、どんな努力をしているのか」を明らかにしたとき、消費者の購入意欲が約30%も高まったという結果が出ています。
最後のステップが、「返報性」です。
返報性というのは、「何かをしてもらったら、お返ししたくなる」という気持ちのことです。
たとえば、懸命に努力している姿を正直に見せられたとき、人は「応援しないと申し訳ない」と思ってしまうことがあります。
この感情が行動につながります。
たとえば、投票をする、商品を買う、SNSでシェアする、などの形で、応援の気持ちを実際の行動に変えていくのです。
こうしてみると、アンダードッグ効果には「感情」だけではなく、「行動を引き出す仕組み」がしっかりあることがわかります。
誰かを応援したいと感じるとき、心の中ではこの3つのステップが動いているかもしれません。
判官びいきとの共通点と違いを比較解説
アンダードッグ効果と似た言葉に「判官びいき」という表現があります。
どちらも「弱い立場の人を応援したくなる気持ち」という点では共通していますが、実は少し違いがあります。
ここでは、その違いをわかりやすく見ていきましょう。
「判官びいき」とは、日本で昔から使われてきた言葉です。
この言葉は、源義経の物語によく表れています。
源義経は、才能がありながらも最終的には追い詰められて悲しい最期を迎えたことで知られています。
そんな義経の姿に、人びとは深い同情を抱き、「義経のような人を応援したい」と感じるのです。
つまり、判官びいきは、日本独特の感情の動きであり、物語や歴史への「情緒的な共感」が中心になります。
一方で、アンダードッグ効果は、国や文化を問わず、世界中で見られる心理現象です。
これは、単に同情するだけではなく、その気持ちが「行動」につながる点が特徴です。
たとえば、選挙の場面で「この候補者は今、苦戦している」と報道されたとします。
すると、その人に対して同情の気持ちが高まり、「この人を応援したい」と思い、実際に投票する行動へつながるのです。
判官びいきは、ドラマや時代劇を見て泣いてしまうような感情的な体験に近いです。
一方、アンダードッグ効果は、そうした感情が「投票」「購入」「シェア」などの具体的な行動に変わる点が大きく違います。
どちらも「弱い側を応援したくなる気持ち」を表してはいますが、判官びいきは「感情の物語」、アンダードッグ効果は「行動を引き起こす心理現象」と整理することができます。
この違いを知っておくと、ニュースや広告を見るときに「なぜ自分はこれに惹かれているのか」が少し見えるようになるかもしれません。
バンドワゴン効果との違いと「逆転現象」を徹底比較
アンダードッグ効果の対になるような心理に、「バンドワゴン効果」というものがあります。
この2つは、正反対のように見えて、実はとてもよく似た場面で発動することもあります。
ここでは、まずバンドワゴン効果の特徴から整理していきましょう。
バンドワゴン効果が起こる3つの条件
バンドワゴン効果とは、「みんなが選んでいるなら、自分もそれに乗っかりたい」と思ってしまう心理です。
いわゆる「勝ち馬に乗る」ような行動ですね。
この効果が強く働くのは、ある3つの条件がそろったときです。
まずひとつ目は、「優勢な情報」が何度も示されることです。
たとえば、テレビ番組やSNSなどで「この商品がいま一番売れています」「この候補が支持率トップです」といった情報が何度も流れてくると、「それだけ人気があるなら、選んで間違いなさそう」と感じるようになります。
次にふたつ目の条件は、「多数派に属することで安心できる状況」があることです。
多くの人と同じものを選べば、失敗が少ない、恥をかきにくい、という空気があると、人は流れに乗りたくなります。
さらに、みんなと同じ選択をすることで、金銭的・社会的なメリットを得られるケースもあります。
たとえば、売り切れ前に買えた、みんなとの話題についていけた、などの具体的な利点ですね。
そして三つ目は、「時間の制限があること」です。
たとえば、「セールは本日限り」「投票締切まで残り3時間」など、判断を急がされると、人はじっくり考えるよりも、「もうこれでいいか」と感覚で決めやすくなります。
こうした状況では、「今いちばん選ばれているもの」をとりあえず選ぶ人が一気に増える傾向があります。
このように、バンドワゴン効果は「多くの人が選んでいる」という情報に触れたとき、その流れに乗ることで安心感を得ようとする心理です。
特に、繰り返しの情報と時間のプレッシャーが重なると、一気にその力が強まります。
一見すると合理的な判断のようでいて、実は無意識のうちに周囲に流されていることもあるのです。
アンダードッグ効果とバンドワゴン効果の違い
アンダードッグ効果とバンドワゴン効果は、どちらも「人が何かを支持したくなるとき」に働く心理です。
ですが、この2つは真逆のタイミングで発動するという特徴があります。
アンダードッグ効果が起きるのは、「今、この人やチームは不利な状況にある」と知ったときです。
その瞬間、「なんとか応援したい」という気持ちが強まり、支援や行動につながるのが特徴です。
このときの感情は、とても個人的で情熱的なものです。
「頑張ってほしい」「報われてほしい」という共感が、ひとつの対象に向かって集中します。
一方で、バンドワゴン効果はまったく逆の動きです。
「今、この人が一番人気だ」「この商品が売れている」といった情報に触れると、「選んでも大丈夫そう」と感じて、安心してその流れに乗ります。
このときの判断は、どちらかというと冷静で合理的です。
「失敗しにくそう」「みんなと同じなら安心」といった理由から、多数派に便乗する形になります。
アンダードッグ効果が「感情的な一点集中」であるのに対して、バンドワゴン効果は「安心感による拡散的な支持」と整理できます。
どちらも人の行動を動かす強い力を持っていますが、働くタイミングも、動機も、まったく違うという点がとてもおもしろいですね。
効果が反転するシナリオと注意点
アンダードッグ効果とバンドワゴン効果は、まったく逆の心理現象ですが、実は「うまく切り替える」ことで連続的に活用できることがあります。
同じ人物や商品でも、見せ方やタイミングによって、起きる効果が変わってくるのです。
たとえば、最初の段階で「資金が底を突きそうです」「今のままでは届きません」といった、劣勢を感じさせる情報を出すと、アンダードッグ効果が起こりやすくなります。
「なんとか応援したい」「このままじゃ終わってしまうかも」という気持ちが生まれ、共感が集まるからです。
そして、ある程度の支援や注目が集まりはじめたら、今度は「支援が急増中!」「予約が続々入っています」といった優勢な情報を発信してみましょう。
そうすることで、次はバンドワゴン効果が働き、「みんなが選んでいるなら自分も」と思う人が増えていきます。
この切り替えの流れは、実際にマーケティングや選挙の現場でもよく使われている手法です。
ただし、注意点もあります。
弱者であることを長く強調しすぎると、「同情を狙っているだけでは?」と受け取られてしまうリスクがあります。
特に、繰り返し「大変なんです」「苦しいんです」とアピールしすぎると、逆に信頼を失ってしまうこともあるのです。
そのため、劣勢ストーリーを語ったあとは、「どこまで回復したのか」「今どう変化しているのか」といった具体的な成果や改善の数字を早めに出すようにしましょう。
たとえば「この3日間で予約数が2倍になりました」といった安心できる情報があると、自然と「今なら間に合いそう」「一緒に成功できるかも」と感じる人が増えていきます。
劣勢から始まって、追い風に乗り換える。
この流れをうまくつくることで、アンダードッグ効果とバンドワゴン効果の“いいとこ取り”ができるのです。
具体例でわかるアンダードッグ効果【恋愛・アイドル・選挙】
アンダードッグ効果は、日常のいろいろな場面で自然と起こっています。
ここでは、恋愛・アイドル・選挙という3つの場面を通して、「どのように人の心を動かすのか」を具体的に見ていきましょう。
恋愛で「劣勢キャラ」が魅力的に映る理由
たとえば、仕事ではとても優秀で、みんなから信頼されている人がいるとします。
そんな人が、ふとしたときにこう打ち明けるのです。
「実はプレゼンが苦手で、毎晩帰宅後にこっそり練習してるんだよね」
それを聞いた相手は、「あの完璧に見えていた人が、自分にだけ弱さを見せてくれた」と感じます。
その瞬間、心の中に同情と共感が一気に広がります。
そして、その人が努力の末にプレゼンで成果を出したとき、「応援してよかった」「自分も力になれたかもしれない」といった満足感が生まれます。
この気持ちが、いつの間にか恋愛感情へと変わることもあります。
この流れには、心理的なしくみが関係しています。
まず、「自己開示」がきっかけになります。
つまり、自分の弱さや本音を相手に見せることです。
すると、それに応じて相手の心にも「返したい」という気持ちが生まれます。
これは「返報性の原理」と呼ばれるもので、人は何かをもらったら何かを返したくなるという心理です。
このとき、「ただ応援したい」という感情が、アンダードッグ効果によってさらに強まり、「好意」や「恋愛感情」へとつながっていくのです。
強い人が、実はどこかに“弱さ”を持っていて、それを努力で乗り越えようとしている。
その姿に、心を動かされるのは、まさにアンダードッグ効果が働いている瞬間といえます。
アイドルや推し活に見るファン心理の動き
まだ知名度がない頃のアイドルグループやアーティスト。
そんなグループを、ほんの数人のファンが応援していた時期があります。
地方の小さなライブ会場に集まった観客は、わずか20〜30人ということも珍しくありません。
でも、初期から応援してきたファンたちは、ビラを配ったり、SNSでひたすら情報をシェアしたりと、地道な応援を続けました。
そのグループが数年後には、全国ツアーで会場を満員にするようになった。
そんなエピソードは、実は音楽業界ではよくある話です。
このときファンが感じるのは、「自分がこのグループを育てたんだ」という強い想いです。
この感情は、心理学では「心理的オーナーシップ」と呼ばれるものに近く、「自分が関わったからこそ成功した」という実感が、長期的な支持につながります。
アンダードッグ効果は、こうした“劣勢の時期”に強く働きます。
ファンはまだ売れていない姿を知っているからこそ、その努力を近くで見てきたからこそ、応援の気持ちが深くなります。
「自分の応援が、少しでも力になったかもしれない」
そんな気持ちがあるからこそ、ブレイクしてからも変わらず支援を続けるのです。
つまり、苦しい時期を一緒に歩んだという物語こそが、ファンとアイドルをつなぐ強い絆になります。
アンダードッグ効果は、ただの“同情”では終わりません。
時間をかけて、一緒に物語を紡ぐような深いつながりをつくっていく力があるのです。
選挙での逆転勝利 世論調査が票を動かす仕組み
選挙では、終盤に予想を覆すような“逆転劇”が起きることがあります。
特に、世論調査で「この候補は劣勢です」と報じられたあとに、急激に票を伸ばすという現象です。
この動きこそ、アンダードッグ効果が強く働いた結果だと考えられています。
有権者が「このままでは負けてしまうかもしれない」と危機感を抱いたとき、「応援しなければ」という気持ちが一気に高まります。
その感情が投票行動につながり、結果として接戦だった選挙区で逆転勝利が生まれることがあるのです。
実際に、こうした動きは複数の研究でも確認されています。
ただし、どんな選挙でも必ず起きるというわけではありません。
アンダードッグ効果が表れやすいのは、次のような条件が重なったときです。
ひとつは「接戦の状況にあること」。
どちらが勝つかわからないほど拮抗していると、危機感や同情が高まりやすくなります。
次に、「投票率が低め」であること。
こうしたときには、一部の熱心な支持層の動きが全体の結果に大きく影響します。
そしてもうひとつは、「メディアの報道が活発であること」です。
テレビやネットニュースで「この候補はいま苦戦中」といった報道が出ると、それが有権者の意識に強く残ります。
このように、メディアによる“伝え方”も、アンダードッグ効果を後押しする要因になります。
だからこそ、「劣勢」「優勢」といった言葉を使うときには注意が必要です。
報道の仕方ひとつで、実際の投票行動が変わってしまうことがあるからです。
このような影響を「アナウンスメント効果」と呼び、報道機関には慎重な配慮が求められています。
選挙報道はただの情報提供ではなく、ときに結果を左右する力を持っている。
アンダードッグ効果が表れる場面では、その力がとても顕著にあらわれるのです。
日本人が弱者を応援しやすい文化背景
日本では昔から、「弱い立場の人を応援したい」という気持ちが自然と生まれる文化があります。
この価値観は、物語や歴史を振り返るとよくわかります。
たとえば、源義経のように、不遇な運命に立ち向かう人物は、時代を超えて多くの人に愛されてきました。
こうした感情は「判官びいき」とも呼ばれ、弱い側に立つ者に心を寄せる気持ちを表す言葉として定着しています。
古典文学の中にも、報われない者に共感するストーリーがたくさん描かれています。
その感情は、現代のスポーツにも引き継がれています。
たとえば、2018年の夏の高校野球では、部員数が少ない地方の公立高校が、次々と強豪校を破っていきました。
この姿に、全国から応援の声が集まりました。
「不利な条件でもあきらめずに挑み続ける姿」に、多くの人が心を動かされたのです。
このように、日本の文化には「弱い者に寄り添う心」が深く根づいています。
そのため、日常の中でも、アンダードッグ効果が自然に働きやすい土壌が整っているといえます。
単なる心理的な反応ではなく、長い歴史の中で育まれてきた価値観が背景にあるのです。
ビジネスとマーケティングでの活用法とNG例
アンダードッグ効果は、ビジネスの現場でもしっかり活用できます。
とくに、スタートアップや中小企業にとっては、強力な武器になることがあります。
では、どんなふうに活かせるのでしょうか?
スタートアップが「弱者ストーリー」を語るメリット
新しく立ち上がったばかりの企業は、大手企業に比べると知名度も資金もどうしても少なくなります。
でも、そこをあえて隠さずに、「資金繰りに苦しみながら、深夜まで試作品を磨いています」といった舞台裏を素直に伝えることで、多くの人の心に届きやすくなります。
こうしたストーリーに、投資家やお客さんは自分を重ねて「応援したい」と思うようになるのです。
たとえば、まだ開発途中の商品であっても、少しずつ進捗を発信していくと「一緒に育てていく感覚」が生まれます。
実際に、クラウドファンディング型のプロジェクトでは、こうしたプロセスの共有が支援の数を増やす傾向にあると報告されています。
「完成していなくても、挑み続けている姿勢」を見せることが大切なのです。
成功しているスタートアップの多くは、こうした“弱者のリアル”を正直に伝えています。
たとえば、資金調達に挑戦したときも、「目標の6割しか集まらなかったけれど、次のマイルストーンには進みます」と誠実に語ります。
このように、格好つけずに今の立ち位置や現実をそのまま見せることで、共感が集まり、支援の輪が自然と広がっていくのです。
「まだ完成していない」からこそ、応援したくなる。
アンダードッグ効果は、そんな“挑戦中の姿”に心を動かされる心理です。
広告コピーでアンダードッグ感を演出するポイント
広告やキャッチコピーで「劣勢でも頑張っている姿」を伝えると、多くの人の共感を得やすくなります。
でも、ここで注意が必要です。
実際には強い立場にある企業が、「小さな会社の孤独な戦い」といった演出をしてしまうと、すぐに見破られてしまいます。
そして、その矛盾がSNSなどで拡散されれば、炎上につながるリスクもあるのです。
だからこそ、アンダードッグ感を出すときには“正直さ”と“根拠”がとても大切になります。
たとえば、「二番手だからこそ改良に時間をかけました」や「あと一歩届かなかった理由は、〇〇でした」といった表現は、弱点を前向きに見せる良い例です。
さらに、こうしたコピーにはデータを添えると説得力が一気に高まります。
「歩留まりが3か月で25パーセント改善しました」というように、改善の成果を数字で示すことができれば、見ている人も「本当に努力してきたんだな」と信頼しやすくなります。
大切なのは、“物語”だけではなく“事実”をしっかり支えることです。
取り繕ったような弱者アピールではなく、本当に乗り越えてきた道のりを、そのまま見せることが、アンダードッグ効果を引き出す近道になります。
SNSキャンペーン成功チェックリスト
SNSで「挑戦中の姿」を伝えると、多くの人から応援が集まりやすくなります。
とくに、スタートアップや個人の活動では「アンダードッグ感」のある投稿が広まりやすいです。
でも、ただ感情に訴えるだけでは長続きしません。
応援を集めるためには、次の3つがそろっていることが大切です。
それが「真摯さ」「継続報告」「感謝の言葉」です。
たとえば、キャンペーンの最初の投稿では「資金が残り30日分しかありません」と、現状を正直に伝えるところから始めます。
その後は、1週間ごとに「進捗」や「課題」を動画などで丁寧に報告していきます。
こうした過程を見守ってくれる人が増えると、支援も自然と集まるようになります。
そして、支援が集まったあとがとても重要です。
「みなさんのおかげで試作品が完成しました」と、成果をきちんと共有すること。
支援してくれた人のハンドルネームを投稿内で紹介するなど、感謝の気持ちを具体的に伝えると、さらに信頼が深まります。
こうした流れがうまく回ると、フォロワーは“ただの見物人”ではなく、“物語の登場人物”のような気持ちになります。
その結果、購入やリツイートが自然に増えていきます。
ただし、途中で報告が途切れたり、感謝の言葉がなかったりすると、「同情を利用しただけなのでは?」と思われる可能性もあります。
共感は、信頼の上に成り立ちます。
だからこそ、継続的に真剣さを伝え続けることが、SNSでアンダードッグ効果を引き出す最大のポイントになるのです。
今日から試せる活用アイデア3選
「アンダードッグ効果、気になるけど何から始めればいいの?」という方へ。
ここでは、今日からすぐに試せる3つの実践アイデアをご紹介します。
どれも難しいことはありません。
少しの工夫で、共感が自然と集まりやすくなります。
まず一つめは、挑戦の過程を日記のように公開することです。
たとえば、「失敗しました→こう直しました→次はこれに挑戦します」と、日々の流れを正直に伝えるだけで大丈夫です。
この“続きが気になるドラマ”のような投稿は、見る人の心を引きつけやすくなります。
二つめは、目標に届かなかった理由と、それに対する改善策を正直にシェアすることです。
そして、「次の進捗は〇月〇日に報告します」と、あらかじめ日付を宣言しておくと、信頼感がぐっと増します。
三つめは、応援やフィードバックをくれた人に対して、感謝をきちんと伝えることです。
「おかげでこの成果が出ました」と、数字や実物を添えて報告すれば、見ている人も「応援してよかった」と感じるはずです。
この3つをコツコツ続けていくことで、「この人をもっと応援したい」と思ってもらいやすくなります。
支援してくれた人は、単なるお客さんではなく、「一緒に物語を作っている仲間」だと感じるようになるのです。
その結果、リピート購入やシェアも自然と増えていきます。
少しずつでもいいので、できるところから始めてみてください。
アンダードッグ効果とは?まとめ
- アンダードッグ効果とは劣勢な立場の人や組織に共感が集まりやすくなる心理現象
- 英語の語源は19世紀の闘犬競技で劣勢な犬を意味する言葉から来ている
- 日本語では「判官びいき効果」と訳されるが文化的な背景が異なる
- 感情から行動へとつながる心理的な3ステップ構造をもつ
- 同情→共感→返報性という順で心理が動き応援行動につながる
- 判官びいきは感情中心だがアンダードッグ効果は行動に結びつくのが特徴
- バンドワゴン効果とは真逆のタイミングで発動する
- 序盤は劣勢アピール→中盤以降は優勢アピールという切り替えが効果的
- 恋愛では努力する姿と自己開示が好意を生みやすい
- アイドル応援では初期の苦労共有がファンの継続支援を引き出す
- 選挙では「劣勢」という報道が支持層の投票行動を促すことがある
- 日本文化には弱者への共感が根づいており効果が表れやすい土壌がある
- スタートアップでは正直な挑戦の物語が投資家や顧客の共感を呼ぶ
- 広告では根拠のある弱者アピールで信頼と行動を得やすくなる
- SNS活用では真摯さ・報告・感謝の三点が共感と行動を持続させる鍵となる